高校時代、私は世界史を選択した。それは通史を年代順に語呂合わせで暗記していくという、今思い出しても“つまらない代物”だった。(当時の先生ごめんなさいm(__)m。)
その後、私は教員となり、神奈川のある私立高校で世界史を教えることとなった。面白い授業を目指して悪戦苦闘する私に、ある先生が話を振ってきた。
「歴史検定なんて俺は持ってないけどさ、役に立つの?って言うか、そもそも歴史を学ぶ本質って何よ?物知り博士になる事なの?」
その先生は数学科の主任だった。確か飲み会の席でのことだったと思う。そう振られて私は「う~ん。」と唸ってしまった。金岡新先生の『世界史講義録』等を読んでいた頃の話だ。『世界史講義録』のおかげで、私の知見は随分と広がったし、生徒が授業に興味を持って臨んでくれている自信はあった。ただ、やはり、通史を年代順に教えていたし、授業は一方通行的なものだった。のみならず「歴史を学ぶ本質」って何か?と問われると、返答に窮してしまった。生徒をあっと言わせるエピソードや因果関係については随分と学んだ。でもそれだけでは足りない。我々が学ぶべき・教えるべき「歴史の本質」って何だ?教える側がそれを解っていないのでは元も子もないのではないか?
それから20年。ずっとそのことを考えてきた。その数学科の主任の先生にはちょっと私一人の背には背負いきれないくらいの【宿題】を出されたと思っている。センター試験は共通テストに代わり、「世界史」は「世界史探求」という科目に変わった。最新の共通テストの世界史の問題を見て見ると、資料を使う問題、情報処理能力を試す問題がほとんどだ。知識そのものより、それをどう扱うか?が問われていたと思う。昔のような単発の知識問題ではなくなっている。ただ、これって要は論理テストの歴史版では?と思う箇所が無いでもない。結局、「歴史を学ぶ本質」が何なのかがはっきりしてないから、論理テストになってしまうのでは?と私などは思う。
では、もう一度、先の宿題に立ち返って「歴史を学ぶ本質」とは何なのか?それを明らかにしてみよう。
以下が私の考える「歴史を学ぶ本質」だ。本当は関係する方々皆様からご意見を伺いたいところだが、そうもいかないので若干チャットGPTの力を借りた。
歴史を学ぶ本質―過去から何を読み解くか?
【全体テーマ一覧(全16テーマ・32時間)】
| 番号 | テーマ | 副題1 | 副題2 |
| ① | 神話と宗教の起源 | 一神教と多神教の違いとは? | 宗教は歴史にどのような影響を与えたのか? |
| ② | 政治と宗教の関係 | 神権政治から政教分離へ | 宗教戦争とその影響 |
| ③ | 民主主義の理想と現実 | 最良の民主主義とは? | 共和制と専制政治の違い |
| ④ | 名君と暴君――指導者の条件 | 名君の条件とは? | 歴史における「名君」と「暴君」の境界線 |
| ⑤ | 帝国の興亡――国家の栄枯盛衰 | ローマ帝国・オスマン帝国・大英帝国はなぜ滅んだ? | 主権国家の病とは? |
| ⑥ | 大航海時代と植民地支配 | 歴史とは誰のものか? | グローバリゼーションの起源 |
| ⑦ | 貨幣と資本主義の歴史 | 貨幣の誕生と経済の発展 | 資本主義の台頭と共産主義という歴史的実験 |
| ⑧ | 経済から見た歴史 | 戦争は政治に従属し、政治は経済に従属する | 貨幣と欲望が動かしてきた世界 |
| ⑨ | 戦争と平和の条件 | 冷戦とは? 核の脅威と軍拡競争 | 戦争はなぜ繰り返されるのか? |
| ⑩ | 地政学から見た歴史 | 地理的要因が国家戦略に与えた影響 | 国境とは何か? |
| ⑪ | 身分制度と社会構造 | 身分制度とは誰のためのものか? | 市民とは何か? |
| ⑫ | 技術革新と社会変革 | 農耕・鉄器・印刷・蒸気機関・インターネット | イノベーションの光と影 |
| ⑬ | 歴史の偽造と修正 | プロパガンダの歴史――戦争・革命・支配の正当化 | 歴史はどこまで「真実」なのか? |
| ⑭ | 民族とナショナリズム | ナショナリズムはどのように生まれ、どのように利用されたのか? | 民族紛争と国家の分裂 |
| ⑮ | 正義と人権の歴史 | 時代や文化によって変わる「正義」 | 人権という概念の誕生とその発展 |
| ⑯ | 歴史を学ぶ意義とは? | 過去を知り、現在を理解し、未来に生かす | 歴史をどう捉えるべきか? 単なる事実か、それとも解釈か? |
始めに断っておくが、通史とは構成が異なるので、早めに大まかな通史を学んで残り時間で、上記の16大テーマ、32の小テーマを学ぶ、もしくは同時進行、あるいは思い切って通史は学ばない。など、そのあたりは工夫が必要だ。(もちろん、これは現時点で私の考えたテーマにすぎません。重複やこのテーマも必要では?などなど様々なご意見が御有りのことと思います。どうぞ、ご遠慮なくコメント欄にお寄せください!)
まず、文科省が、「歴史を学ぶ本質」を明らかにした上で、そのテーマに沿った【共通テスト】なり【入試問題】なりを該当する機関が、各大学が創っていけばよいのでは?と思う。順序としてはそれが正しいのだろう。私ごときがこんな大それたことを提案するなどお門違いも甚だしい。それは重々承知だ。
最後に、やはり歴史を学ぶ上で、伝えたいこと、伝えるべきことってあるのでは?と私は思う。その意味で、うがった見方をするなら、歴史と思想は切っても切れない。それが私の大前提だ。
無論、時代的、社会的文脈次第で、伝えたいこと、伝えるべきことは変わってくる。でもそれでも、それでもやはり、伝えねばならないこと、と言うのがある。それが核の恐ろしさであり、人権という概念の成立過程であり・・・普遍的なテーマだと思う。被爆者の方々が声をあげるのには理由があるのだ・・・。
その意味で「歴史を学ぶ本質」は、やはりテーマありきにならざるを得ない。そして伝えたいこと、伝えるべきこと、伝えねばならないことがある以上、それは多かれ少なかれ、これまた誘導的にならざるを得ない。と言うか、【問い】を設定すること自体もうすでに誘導的なのではなかろうか・・・?その論理に従うなら、授業がある意味誘導的になるのは致し方ない事なのかもしれない。ただ、できるだけ、自主的な授業構成が望ましいのは言うまでもない。これからはできるだけ、一方通行の授業形態は見直されるべきだと思う。
そんなわけで、日本全国の「高校世界史」の関係者の皆さん!どうぞ、忌憚なきご意見を仰ってください。それから、当時の未熟な私に≪ヘビー極まりない宿題≫を出してくださったボンパパことT先生。その節はお世話になりました。これが私なりの解答です!どうぞ、採点・添削をよろしくお願いいたします!
ではまた!
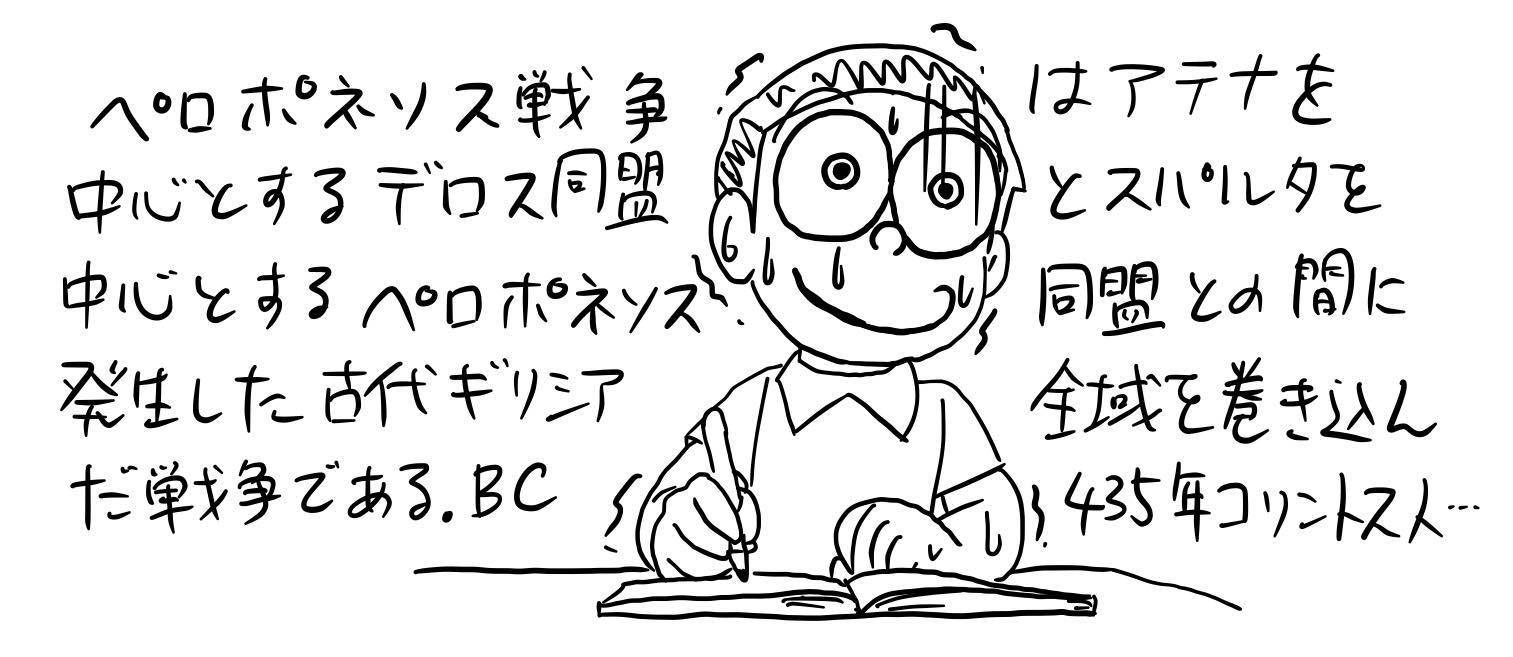

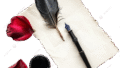
コメント